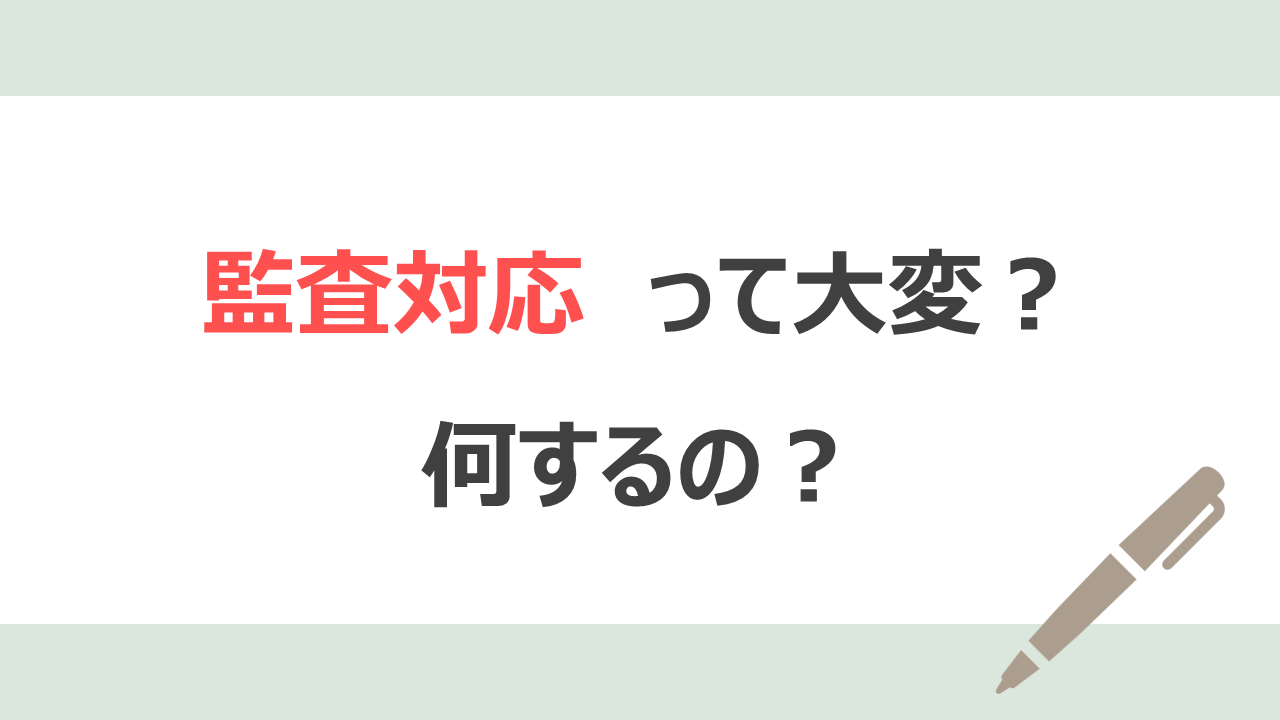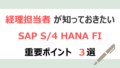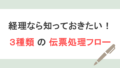経理の仕事には、何やら監査というものがあるらしい。
監査法人に色々聞かれるみたいだけど、なんだか大変そう。どんなことをすればいいのか想像がつかないな・・・。
監査は、経理の仕事の一つ。
この記事を読んでいる皆様も、
- 監査対応は少し経験したことがあるけれど、どんな風に振る舞うのがよいのか分からない
- 自分の担当した監査対応はなんとなく分かるが、監査の全体像が見えていない
- 経理になってはじめての監査対応で、先輩たちから「大変だ」と聞いていて少し怖い・・・
というお悩みをお持ちなのではないでしょうか。
この記事では、経理の仕事の一つである、「監査」について解説します。
この記事を読めば、監査で何をすればいいのか、監査法人とどのように付き合えばいいのかが分かります。監査は毎年必ず行われるものなので、監査を理解すると年次の仕事がグッと楽になりますよ。
監査でやることをマスターして、今後の仕事をスムーズに進められるようにしましょう!
監査とは
監査とは、企業の業務や会計などが、法律や規則、社内ルールなどに従って正しく行われているかどうかを、第三者が客観的にチェック・評価することです。
監査には主に以下のようなものがあります。
- 会計監査
財務諸表が正しく作成されているかをチェックします。公認会計士や監査法人が行います。
例:上場企業が受ける外部監査。 - 内部監査
組織内部の人が業務やコンプライアンス状況をチェックします。経営改善やリスク管理が目的です。 - IT監査(情報システム監査)
システムやデータ管理が安全で、業務に適しているかを確認します。
この記事で取り上げるのは、1.会計監査です。監査法人は内部監査やIT監査でも企業に関わるのですが、経理部で受ける監査は1.会計監査となります。
そのため、この記事で言う「監査」は、「会計監査」のことだと思っていただければと思います。
監査では、監査法人か公認会計士が決算終了後、財務諸表に虚偽がないかを確認します。この確認は四半期ごとに行われており、第一・第二・第三四半期の確認は四半期レビュー、第四四半期の確認は監査と呼ばれます。
なお、財務諸表が正しく作成されているかをチェックする法定監査ができるのは、監査法人または公認会計士に限定されています。そのため、経理に配属されると必ず公認会計士とコミュニケーションを取りながら働くことになります。
監査の時期
監査の時期は、年度決算終了後(4月中旬)~6月中旬くらいまでの、およそ2か月です。
この時期は経理の繁忙期で、特に4月~5月上旬ぐらいまでは忙しいです。
なぜなら、大きな会社だと5月中旬までに「監査報告書」を提出する必要があるからです。監査報告書とは、監査法人または公認会計士が企業などの財務諸表(決算書)について「適正かどうか」を専門的に調査し、その結論を公式に文書で示した報告書のことです。
監査報告書の提出期限が近いので、5月上旬頃には監査法人からさまざまな質問を受けます。それに対応する必要があるので、4月~5月上旬ぐらいまでは経理の繁忙期となるわけです。

経理に配属されたら、残念ながらゴールデンウィークに有給は取りづらいかも。
私の会社では、祝日に出勤することはなかったものの、有給をくっつけて長期休暇にする・・・ということはできず、カレンダー通りに働いていました。
監査期間中の経理の仕事
監査期間中は、通常の業務に加えて監査対応業務を行う必要があるため、とても忙しくなります。
監査対応業務には、以下のようなものがあります。
| 業務内容 | 詳細 |
|---|---|
| 証憑資料の準備・提出 | 請求書、領収書、契約書、稟議書、振込控などを監査人に提出 |
| 監査質問への回答 | 会計処理の背景や判断理由を文書または面談で説明 |
| 残高証明書の取得と提出 | 銀行・取引先等からの残高確認書を取り寄せて監査人に提出 |
| 棚卸資産の立会・報告 | 期末在庫の棚卸に立ち会い、記録や評価方法を提示 |
| 内部統制に関する説明 | 承認フローや分掌管理(誰が何を担当しているか)を説明 |
| 監査人による実査対応 | 現金・有価証券の実物確認に立ち会うことも |
それぞれ、順に解説していきます。
証憑資料の準備・提出
経理は、監査法人や公認会計士(以下、監査人と記載します)から指定された取引の証憑資料を準備・提出する必要があります。
その理由としては、監査人が財務諸表の数値が正しいかを判断するため、ひとつひとつの取引を確認する必要があるからです。しかし、すべての取引を確認していてはキリがないので、監査人は特に重要な取引をいくつか選んで証憑資料を確認しています。

経理の仕事をされていない方に向けて補足すると、証憑資料とは取引の裏付けとなる書類のことです。
経理の仕事は、求められた証憑資料の担当部門(例えば、契約書なら営業部など)とコミュニケーションを取り、必要な資料を社内から集めて、監査法人へ提出することです。
数が多いと面倒な作業になりますが、監査(財務諸表が正しいことの保証)をしてもらうためには欠かせない作業です。
監査質問への回答
経理は、提出した証憑に関する質問を受けたときは、その質問に答える必要があります。
メール等の書面で質問を受けたり、会議中に口頭で聞かれたり様々ですが、もらった質問と回答の内容は必ず文書で記録に残しておくのがおすすめです。
受ける質問としては、例えば特定の仕訳の背景、会計基準の適用理由、見積もりや判断の根拠に関するものなどがあり、多岐にわたります。
少し面倒に感じるかもしれませんが、監査人に「財務諸表が正しいですよ」と保証してもらうためには必要な作業なので、正確かつ論理的に回答するよう心がけましょう。

私が働いていて特に質問が多いなと感じたのは、売上の見積計上に関するものです。
売上の見積計上は、売上が確定していない時点で、売上金額を見積もって計上することを指します。
監査法人としても、架空の売上が財務諸表に含まれているとマズいので、
・その売上が確実に入ってくるのか?
・売上金額は、どのような根拠に基づいて見積もられているのか?
は、たびたび聞かれました。
残高証明書の取得と提出
「残高証明書の取得と提出」とは、主に監査対応の一環として、企業が期末時点に保有する資産や負債の残高について、第三者(銀行や取引先など)から正式な証明書を取り寄せて監査人に提出する作業です。これにより、帳簿上の残高が実在し、正確であることを裏付ける目的があります。
銀行や取引先に対して正式な様式(依頼文)で発行を依頼して、証明書を受領したら内容を確認します。
取り寄せた証明書に記載の金額と、自社で管理している金額に差異がある場合は、その原因を調査したうえで監査人へ提出します。

実際、差異がある場合がほとんどです。
また、銀行や取引先は「自社の監査に協力してくれている」立場なので、提供してもらえる情報にも限りがあり、差異の原因が分からないこともあります。
しかし、経理は自社の会計処理が、基準に則って正しく行われていることを説明できれば問題ありません。「先方との差異の原因は分からないが、ウチはこんな基準に沿って合理的に会計処理している」と監査法人に説明できるようにしておきましょう。
棚卸資産の立会・報告
「棚卸資産の立会・報告」とは、企業が保有している在庫(=棚卸資産)について、期末時点での実在性・数量・評価の正確性を確認・記録し、監査人に報告する業務です。企業と監査人双方でのチェックが行えるよう、監査人が立ち会うこともあります。
監査人は、在庫が実際にあるのか? 数量は正確か? 在庫金額の評価基準(原価・時価・評価減など)が適切か? を確認しています。
在庫も財務諸表に記載する必要がある項目なので、正確性をきちんとチェックしているというわけですね。

経理はあまり出張があるイメージがなかったんだけど、私の会社では棚卸のときは経理の担当者や監査人が全国各地の工場まで足を運んでるよ!
内部統制に関する説明
「内部統制に関する説明」とは、企業が業務の適正性・信頼性を保つために整備している仕組みを監査人に対して説明することを指します。
監査人が企業の財務諸表の正確性や信頼性を評価するうえで、企業が整備・運用している「内部統制」が適切に機能しているかどうかを確認する必要があります。
内部統制とは、企業の“ルールと仕組み”を整え、仕事を正しく、安全に進めるためのシステムです。
たとえば、会社で以下のようなことが起きていると、会社に対する信用が失われてしまいます。
- Aさんが勝手に会社のお金を振り込んでいた → 不正や横領のリスク
- 売上を間違って多く記録していた → 財務諸表がウソになる
- 誰が何をしているか分からない → 責任の所在が不明
こうしたことを防ぐために必要なのが「内部統制」による、“ルールと仕組み”です。
監査法人は、企業の内部統制が機能しているかを確認する必要があるため、企業側はこれに対し、内部統制の仕組み・運用状況・管理体制を説明します。
主な説明内容は、取引の承認フロー(例:請求書は課長→部長→経理で承認 など)や、不正防止のための業務分担の工夫(例:発注と支払は別担当者)、各部門の業務のマニュアルなどです。

私の個人的な感覚ですが、内部統制に関しては、比較的年次の若い監査人が担当していることが多いです。
監査人による実査対応
実査(じっさ)とは、監査人が実際に「現物」を確認することです。
たとえば、「帳簿上に現金が100万円ある」と書いてあっても、本当にそのお金があるとは限りません。そこで、監査人が自分の目で確かめる手続きを行うわけです。
実査によって現物を確認できれば、それはより強い監査の証拠となります。
実査の対象になるものは、現金や有価証券などの金融資産に限らず、取引先との契約書や請求書など、多岐にわたります。

近年は電子化の流れにより、契約書などはPDFが正規の書類として使用されたりしていますが、監査人は紙での契約書を確認したい場合もあるようです。
PDFは簡単に書き換えができてしまうので、印刷した紙の資料と一致しているかを見ておきたい、ということなのですね。
【まとめ】監査人との付き合い方を知り、監査をスムーズに進めよう!
監査は毎年必ず発生するかつ、監査人とのコミュニケーションが必須になる業務です。
監査人に「財務諸表が正しいですよ」と保証してもらうためには、監査人からの様々な質問に答えなくてはいけません。場合によっては経理部門以外とも調整が必要です。
大変な業務ですが、監査を通して監査人が何を確認したいのかを理解することで、業務をスムーズに進めることができます。
以下を参考に、監査についてもう一度復習してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!